【福島レポート】
事実と向き合い続けるエネルギーをくれた人々
原子力災害考証館furusato
事務局長 西島 香織

夜の森自宅前から見える夕焼け
福島第一原発と第二原発に挟まれた富岡町での暮らしを初めて6年目。私たちは、特定復興再生拠点である夜の森地区の一角に家を買い、2025年の1月に引っ越しをした。築50年の年季の入った家屋は、地震で柱の一部にひびが入ったり、梁がゆがんでふすまが開かなかったり・・・といったことは多少あった。でも、夜の森の歴史をよく知る「大先輩」として大切に補修し(といっても最低限だが)、住まわせていただくことになった。
今回は、夜の森での暮らし経過と、その際に寄り添ってくださった方々との経験をつづりたい。そして、この1年間で最も私を支えてくれた大沼章子さんの旅立ちに、心からのご冥福をお祈り致します。
専門知と暮らしのはざまで
実は2024年から、私は新しいチャレンジを始めていた。原子力市民委員会の、福島原発事故部会の運営コーディネーターとして、部会長を補佐する役割に着任したのだ。
市民委員会は、原発事故からの「人間の復興」と原発のない社会を目指す市民シンクタンクとして2013年に発足。現在、8名の委員のほか、アドバイザーも含め各分野の科学者、研究者、弁護士、市民運動家、原発事故被害者など80名以上が所属している。私の恩師である舩橋晴俊氏(元法政大学教授)が初代座長を務めたこともあり、設立当初から注目してきた。
富岡町へ移住してから、私は市民活動や市民科学者があまりに少ないことを憂いていた。2023年の処理水(処理汚染水)放出の際、私の周囲からは「どうして?」という疑問が沸き上がるが、数週間でその話題はふっと消えた。そこに東京電力や経産省・環境省からの情報が洪水のように押し寄せ、上書きされていく。この時ほど、「この地域に市民科学者がいてくれたら」と思ったことはなかった。幸い、海に関してはいわき市の「いわき放射能市民測定室たらちね」が測定を続けてくれている。しかしこの地域(双葉郡、それも原発立地自治体で)には、ほぼ一方からの情報しか入ってこないのだ。
私は痛烈に思った。住民と共に町を歩き、酒を飲みかわせるような市民科学者がいてくれたら。ちょっと疑問に思った時にすぐに「先生!」と駆け込める場所があったら。いつだって町民は丸腰で政府や事業者と向き合わされる。誰もがその問題に関して専門家になれるわけではない。だからこそ、市民科学者との信頼関係構築がこの地域には必須だ。そこで、事故廃炉の町に原子力市民委員会の支部を置きたいというのが、当初の私の切実な想いだった。
そのようなアイデアは市民委員会の運営に関わるということと、部会運営コーディネーターが不在になるというタイミングとが重なり、大変ありがたいことに事務局が私をコーディネーターに推薦してくださったのだった。

原子力市民委員会の様子
原発事故の被害について議論するとき、放射線被ばくについては当然、最新の知見が入り、大変勉強になった。その一方で地元の認識とのあまりのギャップに、心の方がうまくついてこなかった。ここに住んではいけないと言われているような、地域の存続そのものが否定されているような気がしてきてしまった。原発や放射性リスクについて議論する度に、この地域の暮らしが、責められているような錯覚に陥ってしまったのだ。
翻って町内に目を向ければ、引っ越し先の夜の森の除染は進まないままだった。この場所を選んできているくせに「線量を下げろ」というのはおこがましいのか・・・?という気持ちにさえなってきた。しかも「年間1ミリに至るか至らないか」という微妙なラインなのだ。年間20ミリ(あるいは100ミリ)までは許容している国からすると、こんな線量の差異など、気にする価値のないちっぽけな問題だろう。
とにかく毎回の会合のたびに、私は不要にエネルギーを消耗していた。
宇野朗子(さえこ)さんと語った「事実との向き合い方」
そんな中、2024年10月に、原子力市民委員会の公開委員会が福島市で開催され、私も現地まで赴いた。委員の各メンバーから福島の現状や廃炉の問題点などが指摘された。その際、私は市民委員会へのお願い事として「ここに住むことを肯定してほしい」という発言をしてしまったのだ。
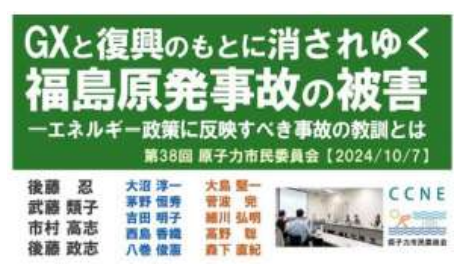
現状の復興政策や廃炉政策に物申したい気持ちで移住したが、日を増すごとに大好きな町になっていくこと。復興政策のために人質に取られている様に感じることもある一方で、「コシアブラの線量が非常に高い」という話を聞くだけで自分自身が否定されているような気持ちになってしまうこと。このように両義的ともいえる日常生活の中で生きており、ディスエンパワーされることが多々あること。それを住民自身が乗り越えるために、まずこの地に足をつけて住むことを肯定してほしいと伝えた。
日本にはチェルノブイリ法のような法律がない。そういった議論を本当はしてきたい。この地に足をつけることを肯定してくださることによって、疑問や不安を発言していいのだと思えるものだ。結果、自治が生まれ、自分の町の未来を自分が決められるようになる人が増えていく。そのために、力を貸してほしい。参画すればするほど、被災地に住む方々(事業者や作業員たちも含め)エンパワーされるような組織になるように、自分も尽力したい。こんな話をした。
発言の後、部会コーディネーターとして「失言だったか」と思ったがもう遅い。私の発言については、委員含め複数のレスポンスがあった。
「課題は、非常に厳しい現実が知らされていないことだと思う。誰かにエンパワーメントされるのではなく、(市民委員会は)現実をはっきり伝え、自分がそれを判断するべきでは。」というご意見。
「私自身、(福島に)危険を承知で暮らしている。毎日繰り返し言い聞かせないといけない。学校が再開した場所の周りが高線量であるという現実にとても胸が痛む。痛みが伴うが、それをみんなで話すことが大事。そこに住む方の存在を否定することはできないけれど、子どもさんも暮らしていることについて、肯定はできないと思う。」というご意見もあり共感した。

地域のお祭りではよさこいを踊ります!
自身も居住を肯定しきれていない中で、私の言う「エンパワー」というのは、まさに「正しい情報(これは、より過酷で厳しい現実を突きつけられるということ)」に向き合うモチベーションを上げることだ。復興の現場、補助金、日々の楽しい暮らしには目を向けやすい。でも終わっていない廃炉、労働者とその家族の安全、被ばく・・・そして原子力政策や避難計画の問題・・・。そうした問題に向き合うための力が、圧倒的に足りていないのだ。
本質的な問題は、情報や知識が足りないという事ではないと私は考えている。否定されればされるほど、事実が突きつけられるほど、自身の価値観や判断が否定されている気がしてシャットアウトしてしまう。「反原発派」とひとくくりにする人もいるかもしれない。対話と発言を促し、ネガティブな真実に向き合う強さと冷静さ、それらが入る余地が残されていない。私はこの地域をそんな風に見ている。
そんなこんなで、やっぱりこの日も、これまでにないくらい消耗して帰ったのだった。駅に佇んでいると、とある人から連絡がきた。
「今日は大変お疲れさまでした。西島さんの発言によって、私たちが必要としているとても大切な対話が開かれたと感じました。勇気をもって、そして深い思慮をもってご発言くださったことを感謝しています。・・・・・・大変な現実の中で、生きることをどんな風に支え合っていけるのか、共に考えたいです。いつか近い日にまたゆっくりお話をうかがう機会がありますように。」
ご連絡をいただいたのが、ほかでもない宇野朗子さんだった。宇野朗子さんは私と同じ埼玉県出身で、福
島市にて被災し、現在は京都に避難中だ。オンラインの対話会「うみたいわ」を運営しながら、原子力災害をどう捉え、どう向き合うか考える場づくりをしている。

宇野朗子さんとのオンラインzoom対話のあとで、「記念写真」

宇野朗子さんらが運営する「うみたいわ」カバー画像
後日、オンラインで90分程度お話しした。ここに来た理由、葛藤などを聴いていただいた。被ばくを避ける権利は、避難した人にも、ここにいることを決めた人にも、等しく与えられてしかるべきということを確認した。「被ばくを避けたい」という気持ちは、ここに住むことを選んだ私も発言して良い。これから住む人たちや、これから万一過酷事故があった際の未来に向けて、それぞれの権利を求めることについて協力できないだろうか。そのような事を話せたことで、とても勇気をいただいた。改めて宇野さんとの出会いに感謝したい。
市民科学者として寄り添っていただいた故・大沼章子さんのこと
もう一人、私に「向き合う」パワーを下さった方がいる。2023年12月、全国26か所の市民放射能測定室をつなぐネットワークであるNPO法人「みんなのデータサイト」運営委員の大沼淳一・章子夫妻ら4名が、浜通りを来訪した。その際、大沼さんから意外な一言があった。
「今回、会ってくれるか心配でした」。「汚染地域」で子育てしながら暮らす私たちのような存在は、まだ少ないのかもしれない。それでも私なりに一生懸命説明した後、章子さんの「あなたがここで何をしたいか、よくわかりました」との言葉に救われ、涙してしまった。これが大沼章子さんとの出会いだ。

近所の赤ちゃんを抱っこする章子さん
丁度、富岡中心部から夜の森北地区への引っ越しを控えていたため、除染と放射線防護について章子さんに伴走していただいた。
前回の寄稿に書いた通り、夜の森に家を買ったのだが、線量に向き合うためのエネルギーが不足していた。子育てと仕事が多忙だったこともあるが、それ以上に、線量が下がらないかもしれないという不安と諦めの気持ちと、「なぜわざわざ夜の森へ」という他者からの問いかけが心を締め付け、私は苦しかった。春なったら子どもたちも庭に出たがるだろう。そういう不安なことから一切逃れたい気持ちになっていた。足が向かない、気が赴かない状況が続いており、体調も悪かったのだそんなときに出会ったのが章子さんだった。
2024年6月にお越しいただいた際には、家の周りを詳細に測定してみたり、土壌を測定してみたり。土をはぎ取った部分は低いけれど、木の根元部分だけを測ると当時の土が混じっており、線量が高くなることもわかった。まずは環境省の高圧水洗浄でどこまで下がるか確認し、次の手を打とうということになった。
環境省に連絡すると、開口一番「かなりガッツリ除染したので、これ以上は下がらないと思いますよ」と言われた。「0.4μSv/h台であればそんなに高くはないです。」
確かにICRP勧告の年間1ミリに届くか届かないか、という微妙なライン。神経質と思われても仕方のない範囲かもしれない。結局半年以上かかって除染の準備を行った。現状調査をし、除染方法の説明を受け、2月7日、やっと除染は実施された。

除染の様子

除染を見守る章子さん
除染当日、章子さんは夜行バスと電車を乗り継いで、雪の降る富岡まで飛んで来てくださった。そんなときも、子どもたちへのお土産のチョコレートを忘れずに。「ここはどうかな、このコケも高圧で削り取れない?」と除染作業員に確認していただきながら、作業は進んだ。
「明日はどうしてもはずせない予定があって、ごめんね」と言いながら、遠い名古屋まで帰っていった。
除染後、8割がた、線量は残るという結果になった。しかし、これまで気づかなかったホットスポットや、高線量の原因がわかった個所もあり、今後の見通しがついたことは成果だったと思う。本当は、地面をすべてコンクリートで覆いなおせば良い。それは環境省自身が一番よくわかっているのだが、「法律上、それはできない」と弁解された。これ以上、線量は下がらない。原発事故から14年が経ち、今の除染の仕方では太刀打ちできないことがわかっていながら、夜の森は解除され、「人の住める町」となってしまったことを痛感した。
この除染プロセスの間、私はもう一つチャレンジをしてみた。富岡町の町政懇談会へ参加し、「夜の森の面的除染をお願いしたい」と発言したところ、予想以上に多くの町民の方からの援護射撃があった。「気になる箇所は除染を検討します」という環境省の回答に対して「スポットで除染しても意味がないから根本的な除染計画を」という反論があり、「除染により線量は低減した」という回答に対して「基準は震災後ではなく震災前と比べるべき」という反論もあった。環境省と町民との間の課題感の差異が明るみになった形だが、質問する勇気をくれたのも章子さんであり、章子さんが事前に提示してくれた夜の森の線量データが背中を押してくれた。
その後も、掃除機ごみやベランダに干した洗濯物等を測定しようということになって、ぼちぼちとメール文通は続いていた。
6月にも、「子どもたちに」とお土産を携えて元気な姿を見せにいらした章子さん。その数週間後、夫の淳一さんから、突然の訃報を聞かされた。自転車での転倒事故が原因だった。もう77歳と聞いており、いつまでご一緒できるかなと思っていたが、こんなに早く突然に、別れの時が来るとは思っていなかった。
章子さんは、ふらりと来てティータイムを一緒に楽しめる市民科学者として、とても稀有な存在だった。彼女がいたからこそ、私は問題に向き合い、前に進むことができた。何より、「ここで暮らしていくこと」について何一つ、彼女の言葉で傷つけられたことはない(きっと心の内では思うところが沢山おありだったと思う、私に対しては黙ってくれていたのだろうと推察する)。いつも私の心の内を気遣ってくれていることは、丁寧なメールの文章からも伝わってきた。
・・・・・
市民委員会のメンバーであることによって、香織さん自身が、放射能問題を考え、福島の未来を考える場・機会を得ることが、大いに意味のあることだと思います。
メンバーとの意見交換や活動の中で、迷ってもいい、しょげてもいい、でも、時には力をもらったり、あげたり、学びと前を向くためのパッションを感じることもあるでしょう。
香織さんは、すでに、富岡町に暮らしながら、富岡町の再生を図る、
原発事故と地震の被災地浜通りからの発信で人脈を作っていこうと決めたのですから、マイナスからプラスまで全てを受け止めて自問自答し、自らの選択で前に進みましょう。
苦しい時は、この人と思う人に伝えましょう(私は非力ながら、いつでも受けますよ)。
・・・・・

甘党で、昼食は断ったものの
ケーキは断らなかった章子さん
私は、これからもずっとこの言葉を胸に抱いていくし、そうした言葉をかけられる人になりたい。
この6年間、常に心揺らぎながら毎日を送ってきた。ここにいる意味は何か、ここで子育てしてよかったのか。それでも、培ったネットワークを武器に我々にできることは、この地に根を下ろして住民自治を取り戻しながら廃炉を完遂する・・・これしかない。
ここでの暮らしを通じて、震災当時のお母さんたちの苦悩を実感できること、この地域が本来持っていた自然の豊かさを知れること、原子力ムラ、廃炉ビジネスの根深さを体感できること、現にこうして市民科学者たちとこの場で未来の話ができること、これら一つひとつが財産である。これらを糧にして地道にたゆまず活動を続けていきたいと思う。
12月20日には、廃炉ロードマップを制作した原子力損害賠償・廃炉等支援機構(NDF) と、市民委員会メンバーが同席し、町民との対話の場を主催するので、ぜひご参加いただきたい。
原子力損害賠償・廃炉等支援機構(NDF)
原子力市民委員会(CCNE)
【著者プロフィール】

西島 香織
埼玉県出身。環境社会学を専攻し、大学卒業後は環境NGOで放射性廃棄物問題やエネルギー問題に関する政策提言活動に携わる。2019年より双葉郡富岡町に移住し、現在6歳児・3歳児の母。原子力災害考証館furusato事務局長。

